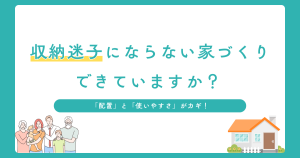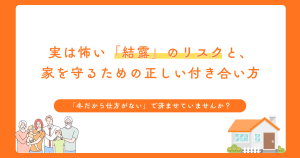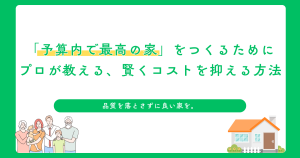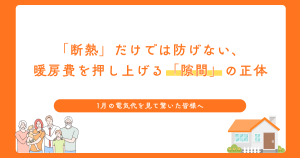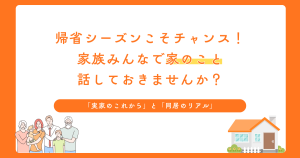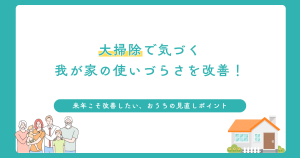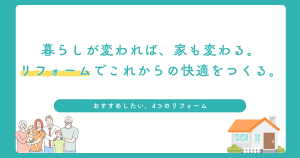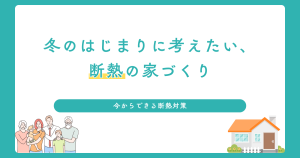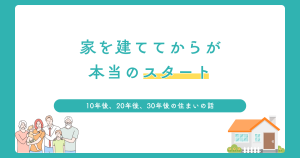「収納迷子」にならない家づくり、できていますか?
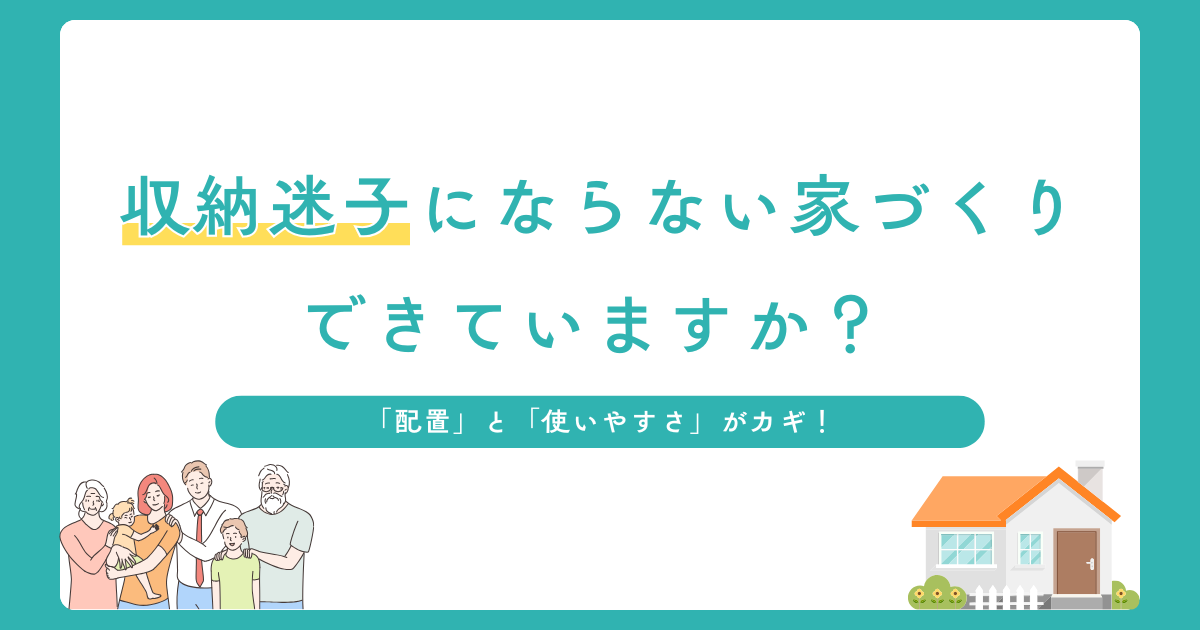
こんにちは!廣谷建設の広報担当です。
せっかく新築するのだから、「収納はたっぷり欲しい!」というご要望はよくいただきます。でも実は、「大きな収納があれば片付く」というわけではないんです。日々の生活で「なぜか片付かない…」「結局、出しっぱなしになる…」と感じたことはありませんか?

どんな収納をつくると、私たちの暮らしに合うんだろう…?
今回は、そんな「収納迷子」にならないための、収納計画の考え方をご紹介します。キーワードは「量」より「場所」、そして「動線との連携」。共働きや子育て中のご家庭にもぴったりの、暮らしに寄り添う収納づくりのヒントをお届けします!
収納の「量」だけでなく、「配置」と「使いやすさ」がカギ!
収納計画というと、「収納量をどれだけ確保できるか」に目が行きがちですが、実際に大事なのは、「必要な場所に」「適した形で」「使いやすく」収納があること。つまり、収納の質が暮らしやすさを左右するポイントです。
とくに朝や夜のバタバタした時間帯に、「わざわざあっちの部屋まで取りに行く」「どこにしまったか分からない」といった場面が増えると、それだけでストレスが溜まってしまいますよね。
玄関収納は「出かける・帰る」動線を意識して
例えば玄関まわりは、ただの下駄箱だけではもったいないエリア。靴はもちろん、コート、カバン、子どもの通園グッズやスポーツ用品、アウトドア道具など、「外に出る」「帰ってきた」ときに使うものをまとめて収納できると、毎日の身支度がスムーズになります。
ファミリー玄関をつくって、生活感を見せずに収納する方法もおすすめです。「ただしまう」だけでなく、「使う→戻す」が自然とできる配置にすることで、家族全員が片付けやすくなるのです。
日常の「動き」に沿った収納計画を
生活動線と収納の配置が連動していると、家事も身支度も格段にラクになります。とくに共働き・子育て世帯では、「朝の準備」「帰宅後の片付け」「食事の支度」など、日々のルーティンに無理なくフィットする収納が欠かせません。
収納が使いにくい場所にあると、どうしても床やテーブルに物がたまりやすくなってしまいます。だからこそ、暮らしの動きに合わせた「場所」と「タイミング」に注目してみましょう。
キッチン横のパントリーは「まとめ収納」と「時短」の味方
買い物のあと、食品や日用品をすぐ収納できる場所があると、とても助かります。キッチンのすぐ近くにパントリーがあると、冷蔵庫やシンクと連携した収納動線が生まれ、出し入れの手間も最小限。さらに、ストック品の在庫も一目で確認できるため、「買い忘れ」や「二重買い」の防止にもなります。
ゴミ箱やリサイクル品の一時置きスペースを併設すれば、キッチン全体がよりすっきり保てます。「調理する人」の目線だけでなく、「家族が片付けやすい」ことも大切なポイントですね。
家族の衣類は1か所に集約がトレンド
最近増えているのが、「ファミリークローゼット」という考え方です。家族全員の衣類やタオル、季節用品などをまとめて収納できるスペースをつくることで、洗濯〜収納の流れが一気に短縮できます。
たとえば洗濯機のあるランドリールームからファミリークローゼットが直結していれば、「干す→しまう→着る」の動線が最短に。わざわざ各部屋に仕分けなくていい分、家事時間の大幅短縮にもつながります。
見た目と使いやすさを両立する収納の工夫
収納がたっぷりあっても、「何がどこにあるかわからない」「生活感が丸出しになってしまう」といった悩みは意外と多いもの。だからこそ、使いやすさと見た目の美しさを両立させる工夫が求められます。
片付けが苦手な方こそ、収納に「ルール」と「余白」を持たせることで、暮らしがグッと整いやすくなります。
扉付き収納で生活感をやさしくカバー
リビングやキッチンなど、家族や来客が集まる空間には、扉付きの収納がおすすめです。たとえばリビングボードや壁面収納に扉を設けることで、見せたくない生活用品やおもちゃ、書類類などをすっきりと隠すことができます。
すべてを隠すのではなく、「よく使う物だけオープン棚に」「それ以外は扉の中へ」と役割を分けると、使い勝手とデザイン性のバランスも◎。おしゃれに見える上に、急な来客時にも慌てずに済みます。
「使う場所の近く」に収納する習慣づけを
リモコン類がソファの周りに散らかる、読みかけの本がテーブルにたまりがち…。そんな悩みも、「使う場所のそばに収納がある」ことで解決できます。たとえばソファ横に引き出し付きのサイドテーブルを置くだけでも、見た目の印象が大きく変わります。
この「使う→戻す」の導線が短い収納は、家族みんなが自然と片付けしやすくなる仕組みにもつながります。「使ったら戻す」の習慣化ができれば、散らかる頻度はぐっと減っていきますよ。
収納は「間取り」と一緒に考える
注文住宅だからこそ、収納スペースも「後から足す」ではなく「最初から暮らしの一部として組み込む」ことが大切です。暮らしやすい収納とは、量だけでなく「位置」と「流れ」が考慮された、生活動線と一体のものです。
収納計画は「動線」と「用途」のセットで
たとえば、帰宅後の流れを想像してみましょう。玄関に入って、上着やバッグ、ランドセルをしまう場所があるだけで、リビングに物が散らかりにくくなります。洗面室の近くにタオルや着替えの収納を確保することで、家事の手間も減らせます。
このように、日々の行動と収納の配置をセットで考えることで、「しまいやすさ」も「取り出しやすさ」も格段に向上します。
家族の成長やライフスタイルの変化も想定して
子どもが小さいうちはおもちゃや絵本、成長するにつれて学用品や部活道具、そして将来的には家を離れる可能性もあります。収納はその時々の暮らし方に合わせて、使い方を変えられる「可変性」があるとベストです。あらかじめ「ここは将来、別の用途に転用できるように」と考えて設計することで、長く快適に住み続けられる住まいになります。
以上、「収納迷子」にならない家づくり、できていますか?というテーマでお届けしました。
次回も、家づくりに役立つテーマを分かりやすくご紹介していきますので、どうぞお楽しみに!
.png)