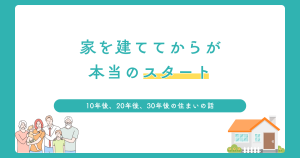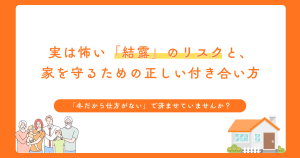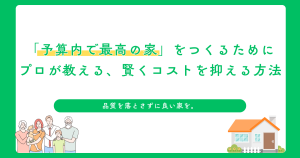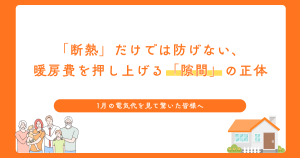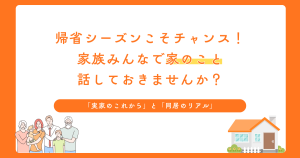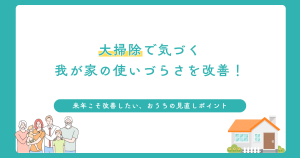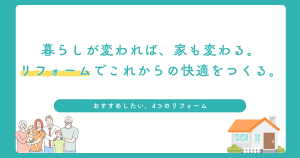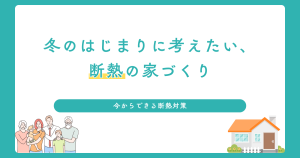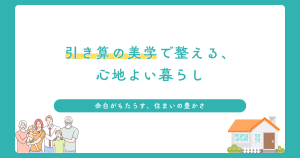「家を建ててからが本当のスタート」10年後、20年後、30年後の住まいの話
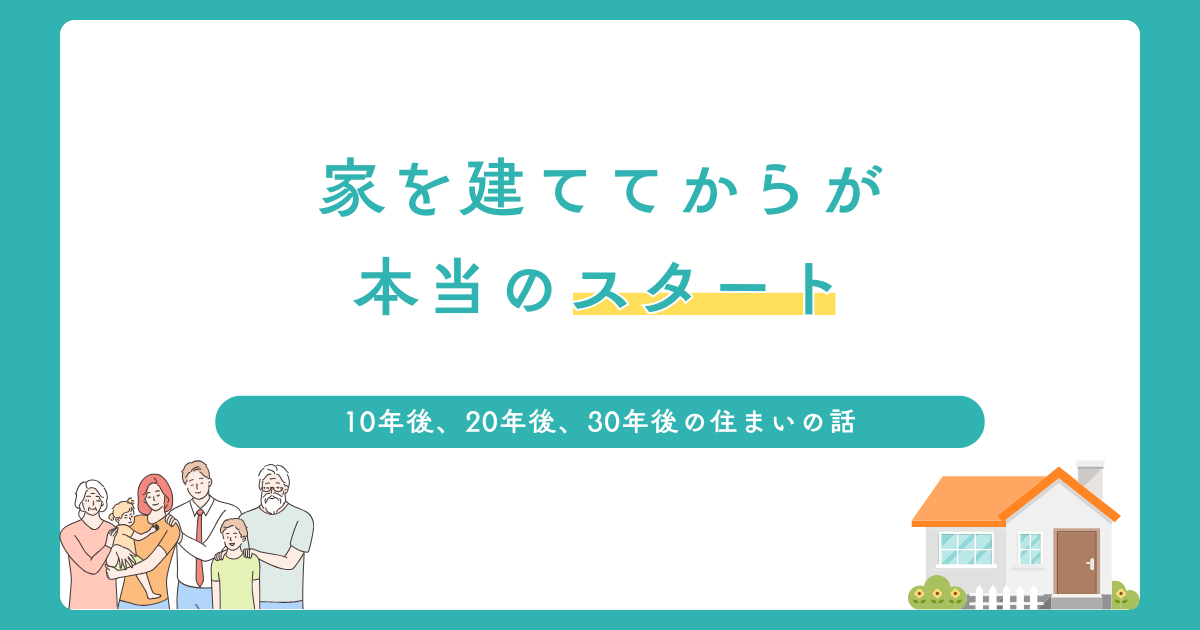
こんにちは、廣谷建設の広報担当です。
家づくりというと、「完成したときがゴール」と思いがちです。でも、実はそこからが本当のスタート。家族の暮らしは日々変化していきます。たとえば、お子さんの成長や独立、仕事や趣味のスタイルの変化、さらには老後の生活まで、そのすべてに住まいは関わってきます。
だからこそ、家を建てるときには「いま住みやすいか」だけでなく、「将来どんな暮らし方になるか」も想像しておくことがとても大切です。今回は、家を建ててから10年、20年、30年経ったあとに「よかった!」と思える住まいをつくるために、いま知っておきたい視点をお届けします。
家を建てた「10年後、20年後、30年後」、どんな変化が起こる?
家族構成の変化(子どもの成長、独立、二世帯化)
家を建てたときには小さかった子どもが、5年もすれば小学生、10年もすれば高校生・大学生というケースも多いでしょう。それに伴い、子ども部屋の使い方やプライバシーの取り方も変わっていきます。
また、将来的に親との同居を考えているご家庭では、完全同居なのか、玄関や水回りを分けた二世帯にするのか、といった構想があるかどうかで、間取りの考え方が大きく変わってきます。
ライフスタイルの変化(在宅勤務・趣味・老後生活)
最近では、働き方の多様化により「在宅勤務」が当たり前になってきました。「将来、在宅ワークになるかも」と想定していなかったご家庭が、「静かなワークスペースがほしい」「リビングでZoomはつらい…」と感じる場面も増えています。
また、趣味の空間(ガーデニング・DIY・音楽)や、老後を見据えたバリアフリーの設計など、「将来の自分たち」にフィットするかどうかも大切なポイントです。
「こうしておけばよかった!」後悔しがちなポイント
収納の使い勝手
家を建てた後の「もっとこうすればよかった……」という後悔の中で、最もよく聞かれるのが「収納」に関することです。特に「モノが増える想定が甘かった」「使う場所に収納がなかった」といった声が多く聞かれます。
暮らしてみて初めて気づくのが、「収納の量」ではなく「収納の位置と動線」の重要性です。たとえば、リビングに必要な掃除用具や日用品が離れた場所にあると、ちょっとした片付けでも手間がかかりがち。結局、出しっぱなしになってしまうことも。
暮らしの「習慣」や「行動パターン」を想像して収納計画を立てておくことが、後悔しないコツです。
動線と間取りの見落とし
毎日の生活をスムーズにするためには、「動線設計」がカギになります。家事や育児をしながら生活するなかで、「洗濯動線が長すぎた」「朝の支度で洗面所が混雑する」といった問題が出てくることも。
こうした問題は、間取りを決める段階での「想像不足」が原因のことが多いのです。設計段階で「実際の生活」をシミュレーションし、「朝は家族3人が洗面を使う」「週3回は洗濯をする」「休日はベランダで過ごす」など、具体的な生活の流れを紙に書き出してみるのがおすすめです。
未来を見据えた「設計の工夫」とは?
可変性のある間取りづくり
長い目で見て住まいを快適に保つためには、「変化に対応できる設計」が大切です。たとえば、2つの子ども部屋を将来1つにまとめられるような構造や、書斎を客間に転用できる配置などが考えられます。
廣谷建設でも、「将来どう使い方が変わっていくか」という視点を共有しながら設計を進めることを大切にしています。お施主様ごとに暮らしの優先順位は異なりますので、まずは「今」と「10年後」の両方に寄り添った設計の考えで進めていきましょう。
メンテナンスと耐久性
また、住まいの「経年劣化」にも目を向けておきたいところ。たとえば外壁材や屋根材、配管設備など、長く快適に暮らすにはメンテナンスのしやすさ・しにくさが住み心地を左右します。
建てるときに少しだけ費用をかけてでも、メンテナンスしやすい素材を選ぶ、更新しやすい構造にしておくなどの工夫をしておくと、10年後、20年後の負担が格段に減ります。
断熱・耐久性など見えない部分への配慮
家づくりでは、間取りや内装のように「目に見える部分」につい注目しがちですが、長く快適に暮らしていくためには「見えない部分」こそが重要です。特に、断熱性能や耐久性は、年月が経つほどその差が実感される要素。断熱性が高ければ冷暖房効率が上がり、光熱費の節約にもなりますし、家全体の温度差が少ないことでヒートショックのリスクも抑えられます。
また、構造材や外壁などの耐久性は、将来のメンテナンスコストを左右する大きな要因。初期段階から「長持ちする素材」「劣化に強い設計」を選んでおくことが、住まいの寿命を延ばす鍵となります。
まとめ………「10年先も快適」と言える家にするために
人生は常に変化し続けます。子どもの成長や独立、働き方や趣味の変化、そして老後の過ごし方まで、家族のカタチが移り変わる中で、住まいがその変化に対応できることが理想です。
以下のような視点で家づくりを考えることで、「10年先、20年先、30年先も快適」な暮らしを実現しやすくなります。
- 「今」と「将来」のバランスをとる視点
家族の今にぴったりな間取りにしつつも、将来の変化に柔軟に対応できるように設計段階から工夫を。 - 長く住まうことを前提とした素材・仕様の選択
劣化しにくい素材やメンテナンス性の高い設備を選ぶことで、長期的な満足感とコストパフォーマンスを高めることができます。 - 時間とともに育つ家づくりの視点を再確認
ライフステージの変化と共に家も育っていく。そんな成長する家という意識を持つことが、家づくりの成功につながります。
廣谷建設では、完成時の美しさや利便性だけでなく、「住んでからの変化」まで見据えた家づくりを大切にしています。今だけでなく、10年後、20年後、30年後の暮らしを見据えて、ぜひ一緒に理想の住まいを考えていきましょう。
.png)