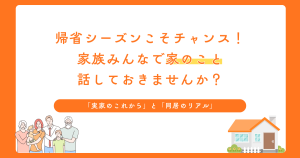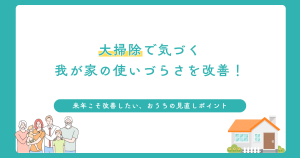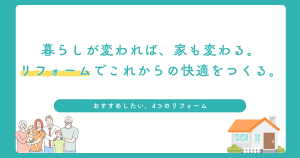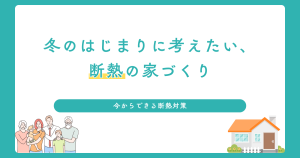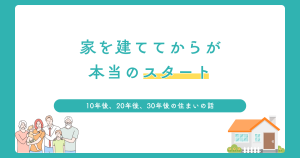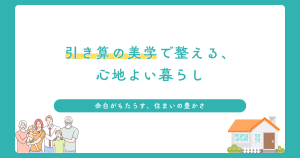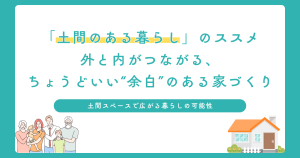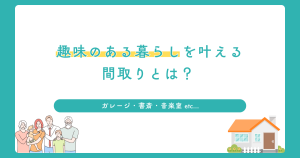5月から始める!失敗しない資金計画の立て方──住宅ローンや諸費用、今のうちに整理しておきたいお金の話
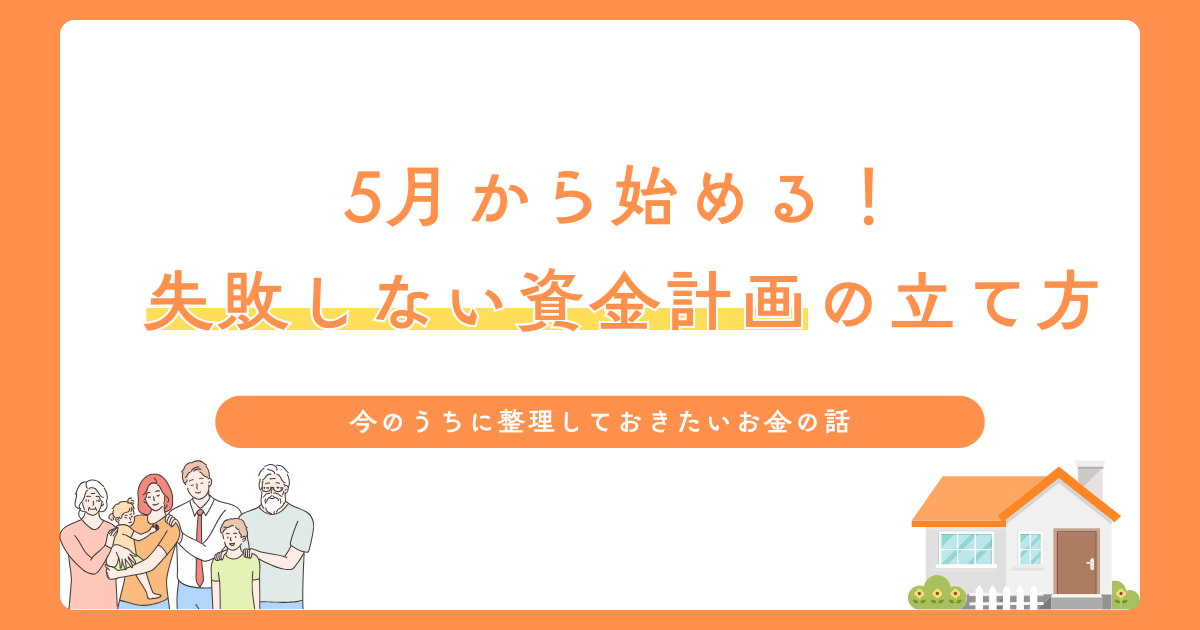
こんにちは!廣谷建設の広報担当です。
「そろそろ家を建てたい」と思っていても、いざ具体的に動こうとすると、最初に不安を感じるのが「お金」のことではないでしょうか。家づくりにはどれくらいの費用がかかるのか、自分たちにとって無理のない予算はいくらなのか、そして住宅ローンはどう選べばいいのか…。どれも一度は考えておきたい大切なポイントです。
5月は新年度の慌ただしさも落ち着き、暮らしを見直すのにちょうど良いタイミング。この時期に資金計画の基本をしっかり押さえておくことで、夏以降の家づくりの進行もスムーズになります。
今回は、家づくりを検討中の方に向けて、「失敗しない資金計画の立て方」をテーマに、わかりやすくお話ししていきます。「資金のことはまだ後でいいかな」と思っていた方にこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。
資金計画を立てる前に知っておきたい全体像
家づくりにかかるお金と聞くと、「建物の工事費」だけをイメージされる方が多いかもしれません。しかし実際には、家づくりにはさまざまな費用が含まれており、総額を正しく把握することが資金計画の第一歩となります。
まず基本となるのが「本体工事費」です。これは建物そのものの建築費で、キッチンやお風呂などの住宅設備、基礎や構造、内装・外装といった住まいの主要な部分にかかる費用です。ただし、これだけでは住める状態にはなりません。
ここに追加されるのが「付帯工事費」です。たとえば、給排水工事や電気引き込み、エアコンの設置や照明工事、地盤改良が必要な場合の費用などが含まれます。地域や敷地の状況によって変動があるため、見積もりの段階でしっかり確認することが大切です。
さらに「諸費用」と呼ばれるお金も見落とせません。これは住宅ローンの手続きにかかる費用(事務手数料、保証料、印紙代など)、登記費用、火災保険料、建物表示登記・保存登記などが含まれます。一般的に、建物価格の6~10%前後と見込んでおくと安心です。
加えて、「土地代」がかかる場合もあります。土地付きの建売住宅でない限り、多くの方は土地の取得費用も含めて考える必要があります。さらに、外構工事(駐車場、塀、アプローチなど)や、引っ越し費用、新たに購入する家具や家電なども家づくりの予算として組み込んでおくと、後から資金に無理が出ません。
つまり、家づくりに必要な資金は、「建てるためのお金」だけでなく、「暮らし始めるためのお金」「将来を見据えた備え」まで含めて考えることが大切なのです。
住宅ローン、どう考える?
家づくりにおいて住宅ローンは、多くの方が利用する重要な資金手段です。ですが、「どのくらい借りられるのか」「月々どれくらいの返済になるのか」「どの銀行を選べばよいのか」など、悩みが尽きないのもこの住宅ローンです。
まず大前提として意識していただきたいのは、「借りられる額」ではなく「返せる額」で考えるということです。金融機関は年収や勤続年数、他の借入状況などをもとに「借入可能額」を提示してくれますが、その上限いっぱいまで借りるのが良い選択とは限りません。月々の返済が生活を圧迫してしまっては、本末転倒です。
では「返せる額」はどう考えればよいのでしょうか。ひとつの目安となるのが、返済負担率です。これは年収に対する年間返済額の割合で、住宅ローンでは一般的に20〜25%以内が無理のない範囲とされています。たとえば年収500万円のご家庭であれば、年間のローン返済額は100〜125万円、月額にして8万〜10万円が目安となります。
住宅ローンの種類も多岐にわたります。地元の地方銀行、信用金庫、大手都市銀行、ネット銀行、そしてフラット35など、それぞれに金利や手数料、審査基準が異なります。最近ではネット銀行の低金利が注目されていますが、地域密着の銀行では相談しやすさや保証内容で選ばれる方も多く、自分たちの重視したいポイントに応じて比較することが大切です。
次に迷いやすいのが、「固定金利」か「変動金利」かという選択です。固定金利は返済額が一定で安心感がある一方、変動金利は金利が低めに設定されており、借入初期の負担は軽くなります。ただし、今後の金利上昇リスクもあるため、長期的な視点で総返済額やライフプランと照らし合わせることが必要です。
返済期間の設定も大きなポイントになります。一般的には35年返済を選ぶ方が多いですが、60歳、65歳といった定年退職のタイミングを見据え、退職後の負担をどうするかも含めて考えておく必要があります。繰上返済の計画を立てたり、ボーナス返済を併用するかどうかも選択肢の一つです。
また、団体信用生命保険(団信)も見落とせない要素です。万が一に備え、ローン残債が免除される仕組みですが、保障内容はローン商品によって異なります。三大疾病特約やがん特約など、手厚い保障を選べばその分金利が上がることもありますので、保障と金利のバランスを見極めることが求められます。
最後に、住宅ローンには「事前審査」と「本審査」という2つのステップがあります。事前審査では借入可能性を簡易的にチェックし、本審査ではより詳細な書類や内容に基づいて金融機関が最終判断を行います。いずれも、廣谷建設では必要な書類の準備や申し込み手続きのサポートを行っておりますので、はじめての方もご安心ください。
見落としがちな「諸費用」と「将来の出費」
住宅の建築費やローンの返済に目が行きがちですが、家づくりにおいて意外と見落とされやすいのが「諸費用」と「将来に向けた支出」です。ここをしっかり押さえておかないと、予算オーバーや暮らし始めてからの「想定外の出費」に頭を抱えることにもなりかねません。
まず、「諸費用」にはどのようなものがあるのでしょうか。代表的なものを挙げると、以下のような項目があります
- 登記費用(所有権保存・抵当権設定など)
- 住宅ローンの事務手数料・保証料・印紙代
- 火災保険料・地震保険料
- 引っ越し費用・仮住まい費用
- 水道加入金や都市ガス接続費(地域による)
- 地盤改良費(地盤調査の結果によっては追加)
- 雪国特有の設備費(融雪設備・屋根形状の工夫など)
これらは、建物本体価格とは別にかかる費用で、一般的には総予算の10%程度を目安に準備しておくと安心です。実際には、建てる地域や敷地の状況、選ぶ金融機関などによって金額が変わってきますので、事前にしっかりヒアリングと見積もりを行うことが重要です。
また、家を建てるときに見落とされがちなのが、「建てた後」の支出です。家づくりとは関係ない費用もありますが、大きな出費はきちんと想定しておいた方が安心です。代表的なものとしては、以下のような費用があります
- 子どもの教育費(塾・進学・習い事など)
- 車の購入・維持費
- 医療・介護など突発的な支出
- 老後資金や住宅ローン完済後の生活設計
- 住宅の定期メンテナンス費用(屋根・外壁・設備など)
たとえば、10年後に外壁の塗装、15年後に給湯器の交換、20〜30年後には屋根材やクロスの張り替えなどが必要になることもあります。こうしたメンテナンス費用は、住宅の寿命を延ばすためにも必要不可欠な出費です。ローン返済中だからといって後回しにすると、住宅の劣化や修繕コストの急上昇につながることも。
そのためにも、「毎月の住宅ローンは多少余裕を持たせておき、いざという時の貯蓄を無理なく続けられる設計」にしておくことが、家計の健全性を保つうえでも大切です。
廣谷建設では、住宅の建築だけでなく「その後の暮らしまで含めた資金計画」をご提案しています。「建てたら終わり」ではなく、「建てたあとも安心して暮らせる」こと。それが私たちの考える「本当の意味での家づくり」です。
無理のない資金計画で、安心の家づくりを
家づくりは、「どんな家に住みたいか」という夢を叶えると同時に、「どれだけ無理なく暮らせるか」という現実とのバランスが求められるものです。特に資金計画は、家を建てる前はもちろん、住んでからの安心感にも直結する重要なステップです。
廣谷建設では、間取りやデザインだけでなく、お金に関する不安や疑問にも丁寧に向き合い、お客様にとって本当に納得できる家づくりをサポートしています。自己資金のバランス、住宅ローンの選び方、諸費用の考え方、将来の出費への備え方まで、家計とライフプランの両面からご相談いただけます。
夢のマイホームは、「建てる」だけで終わりではありません。「建ててからの暮らし」こそが本当のスタートです。資金の面からも安心できる計画を立てることで、その後の暮らしがぐっと快適で前向きなものになります。
これから家づくりを進めたいとお考えの方は、ぜひ5月のこのタイミングで、一歩踏み出してみませんか?廣谷建設では、お客様一人ひとりの「現実的で理想的な家づくり」を一緒に考えていきます。お気軽にご相談ください!
.png)